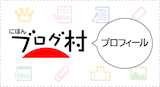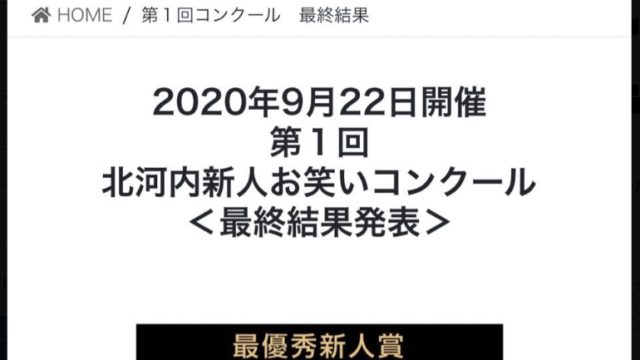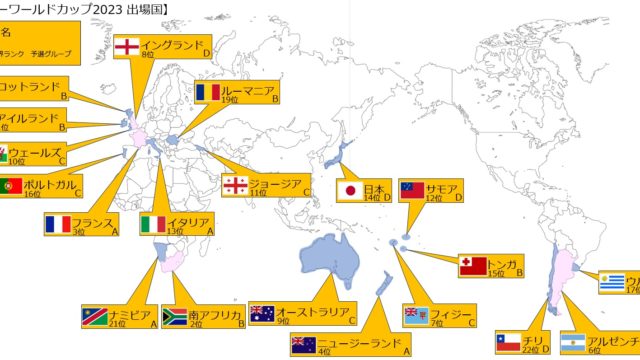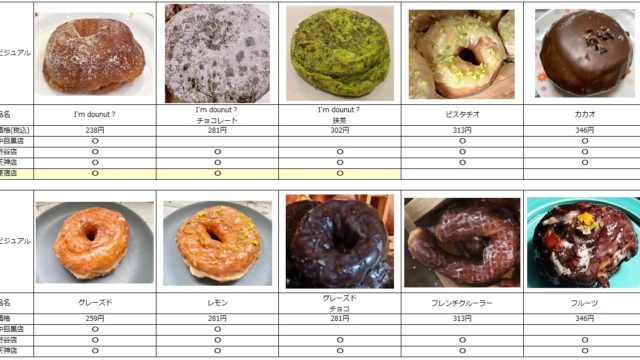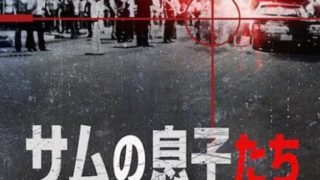TOKIOでお馴染み「ザ!鉄腕!DASH!!」にて
宮城・気仙沼大島の郷土料理が紹介されました。
その中で「あざら鍋」が話題になりましたが
「あざら」とは?由来はどこからきているのか?
まとめてみました。
あざら とは?
気仙沼の郷土料理
「めぬけ」を頭から尻尾まで余す事なく使い、酒粕と白菜漬を使った、体温まるお鍋です。
白菜漬は、お鍋の中ででも食感が活き、めぬけのアラから美味しい出汁が染み出し、酒粕がコクと深みを出して汁まで飲み干せます。
元々は旧正月に各家庭の残り物を煮たところから始まったと言われます。
また、春を迎えて白菜の処理に困った家庭で考案されたという説もあります。
現在、一般家庭ではほとんど作られておらず、小料理屋で出される程度です。
「めぬけ」とは?

メヌケはスズキ目メバル科に属する魚の総称で、その中でも体が赤く大型の海水魚を指して呼ぶことが多い。
体長は40~60cm程度にまで成長し、鮮やかな赤い体色が特徴。
北海道から千葉県の相模湾辺りに生息しており、水深200~1000mの深海を好む。メヌケという名前は目が抜け出て見える外見から付けられました。
ちなみにメヌケの目が飛び出ているのには深海魚の体の構造が関係しています。
深海に棲む魚は基本的に強い水圧に順応できる体をしているため、水面に出たときに急激な水圧の変化に耐えられず、内臓や目が飛び出てしまうのです。
[引用]船釣りマガジン
名前の由来は?
お坊さんであった阿闍梨(あじゃり)さんがつくった精進料理が訛って「あざら」になった説や、
調理方法が荒々しいという意味の古語である「あじゃら」が「あざら」になったなど
諸説あるようです。
作り方(例)
- 白菜の古漬けを軽く絞り、食べやすく切る
- 鍋にバラメヌケ(メヌケ)のあらと白菜の古漬けを入れ、具材がかぶる程度の水を入れて煮る
- 煮詰まってきたら酒粕を入れる
- 混ぜながらさらに弱火で煮込み、仕上げる
- 白菜の塩具合を見ながら少し醤油を入れるとコクが出る。また、酒粕を入れると焦げやすくなるので注意する。