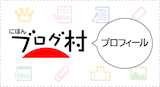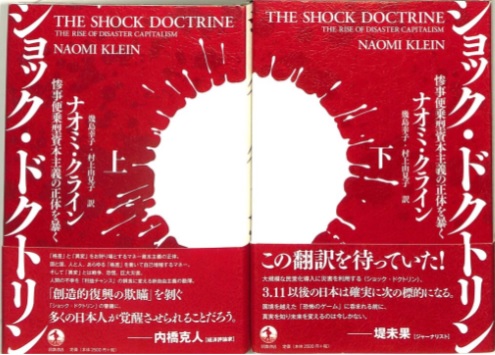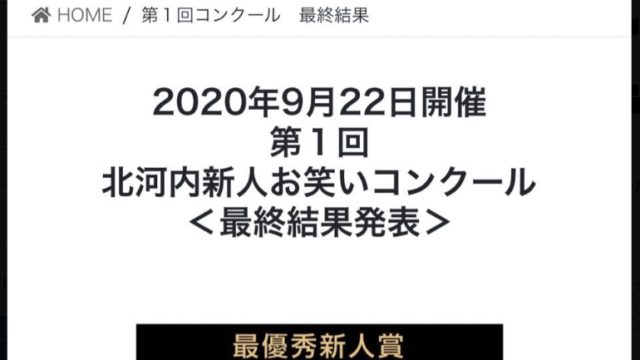飯盒炊爨:はんごうすいさん
あれ?
飯盒炊飯:はんごうすいはん
じゃないの?
と思われる方も多いはず。(私も炊飯の認識でした)
1つ1つ意味を追っていくと由来が見えてきました。
「炊爨」と「炊飯」 辞書での意味は?
炊爨(すいさん)
〘名〙 飯をたくこと。煮たきすること。炊事。
※菅家文草(900頃)一〇・為小野親王謝別給封戸第三表「肩舁二野蔬一、以助二黎民之炊爨一」
※篝火(1939‐41)〈尾崎士郎〉二「雨のために諸隊の炊爨(スイサン)は不可能になったので」 〔礼記注‐月令・季冬〕

炊飯(すいはん)
〘名〙 飯をたくこと。また、食事の用意をととのえること。
※山鹿語類(1665)二一「次に炊飯の宅あり。これに三段をまうけて、魚鳥を調へ包丁を致すの所あり、火を盛にしてこれを煮炙り、あつものし飯かしぐの所あり」 〔論衡‐知実〕
意味は同じのようだが、微妙な違いがあるようです。
炊爨の始まりのほうが昔。「諸隊」から、屋外で行っている様子。
炊飯は比較的近代。「宅」から、屋内で行っている様子。
これを見る限りでは、飯盒は「炊爨」のほうが近そうですね。
「爨」と「飯」 辞書での意味は?
爨(さん)
- かしぐ。飯をたく。「爨婦」「炊爨」
- かまど。「三世一爨」 類 竈(ソウ) · 下つき. 薪爨(シンサン)・炊爨(スイサン).
飯(はん)
- めし。いい。ごはん。「飯米」「炊飯」
- 食事。また、養う。「飯台」「飯店」
「爨」は「かまど」や「薪爨」という言葉もあることから、
やはり飯盒は「炊爨」が適していることが分かります。

まとめ
「飯盒(はんごう)でお米を炊くこと」は「はんごうすい“さ”ん」あるいは1字違いの「はんごうすい“は”ん」と呼ばれるが、これは漢字の違いに由来するとか。前者「~さん」は「爨」(かまど)という字を使った「飯盒“炊爨”」。難しいけど、こちらが本来の書き方。対して、後者「~はん」は「炊飯ジャー」の字をあてた「飯盒“炊飯”」。意味は分かりやすいけど、辞書に載っていない場合もある書き方。
[引用]ねとらぼアンサー
「適している」⇔「言いやすい」
これは世代によって意見が分かれるところですが、
もし言い争いになりそうになったら、本記事を参考にしていただけたら幸いでございます。